こんにちは、FP資格保持者で投資歴7年以上、3人の子を持つ家庭持ちのやまかぜです。
今回は、これから資産形成を本格的に始めたい方に向けて、非常に大切なテーマをお届けします。
それは「保険は本当に必要なのか?」「必要な人と必要でない人の違いは何なのか?」という問題です。
日本では、「保険は入っておくもの」「安心のために必要」というイメージが根強いですが、これは本当でしょうか?
結論を先にお伝えすると、保険は「万が一に備える」ものですが、資産形成においてはむしろ不要な場合も多く、必要なのは一部の条件に当てはまる人だけです。
この記事では、
保険の本質
保険が必要な人と不要な人の違い
具体的な判断基準
無駄な保険でお金を失わないためのコツ
資産形成と保険のバランス
について、FP視点で詳しく解説していきます。
これを読むだけで、あなたは「なぜ保険に入るべきなのか」「どこまで必要なのか」その基準を自信を持って判断できるようになります。
—
【第1章】保険の本質を知る
保険とは、「万が一の時に、家計が破綻しないようにするもの」です。
しかし、「保険に入っておけば安心」という感覚で不要な保険に入り続けると、資産形成の最大の敵 — 「固定費のムダ」 — になります。
保険の役割
保険の役割は大きく分けて2つです。
1. 突然の大きな出費に対応できない場合のリスクヘッジ
2. 社会的に守るものがある人の経済的防衛
つまり、自分で対応できるリスクに対して保険は不要。
自分では対応できないリスク(数百万円〜数千万円単位の損失)に対してだけ、保険は有効です。
例:
車の任意保険(対人無制限)は必要。事故で億単位の賠償が発生する可能性があるから。
数万円程度の医療費なら、貯蓄や高額療養費制度でカバー可能。
—
【第2章】保険が必要な人とは?
では、保険が必要な人はどんな人でしょうか?
ここでは条件を明確にします。
1. 守るべき家族がいる人(特に未成年の子どもや配偶者)
未成年の子どもがいて、教育費や生活費を自分の収入に依存している場合、自分が亡くなった時の影響は甚大です。
死亡保障は必要不可欠です。
> 【目安】
住宅ローンがあるなら団信でカバー
さらに教育費や生活費をまかなうなら、定期保険2,000万円〜3,000万円程度が理想
2. 貯蓄がまだ十分でない人
「現金・流動性資産」が300万円以下しかない場合は、突発的な病気や事故に備える保険は検討の余地があります。
とくに子育て世帯や自営業者は、公的保障だけでは足りない場合があるため。
3. 一家の大黒柱(収入源が自分1人の場合)
家庭の収入のほとんどが自分一人であれば、その収入が止まった時の備えは絶対に必要です。
例:
自分が入院で1ヶ月働けなくなった時に収入がゼロになる場合→所得補償保険が有効。
—
【第3章】保険が不要な人とは?
反対に、保険がいらないケースは次の通り。
1. 独身で守るべき家族がいない人
死亡保険は全く不要です。
亡くなっても経済的に困る人がいないなら、無駄なコストです。
葬儀費用などは現金100万円程度あれば十分。
2. 十分な現金や資産がある人
金融資産が1,000万円以上あり、高額療養費制度や国民健康保険・社会保険制度を理解している場合、医療保険や小さなリスクへの備えは必要ありません。
現金で対応した方が経済合理性が高いです。
3. 公的保障でカバーできる人
会社員の場合、傷病手当金、遺族年金、労災、雇用保険などの制度で、ある程度のリスクは網羅されています。
この制度を知らずに無駄な保険に入っている人は多いので、一度見直しましょう。
—
【第4章】具体例でわかる保険の要不要シミュレーション
例1:30代独身・年収400万円・貯蓄300万円
死亡保険:不要
医療保険:不要(高額療養費で対応可能)
がん保険:不要(貯蓄で対応可能)
自動車保険(対人無制限):必須
例2:40代・既婚・子供3人・住宅ローンあり・貯蓄200万円
死亡保険:2,500万円程度の定期保険を推奨
医療保険:掛け捨てなら検討
がん保険:高額療養費+備蓄で基本不要だが不安なら掛け捨てで
自動車保険:必須
例3:60歳・資産1億円・子供独立済み
死亡保険:不要
医療保険:不要
がん保険:不要
自動車保険:最低限
—
【第5章】無駄な保険に入ってしまう理由と心理
多くの人が保険を「貯蓄代わり」として加入してしまいます。
しかし保険は金融商品であり、保険会社の利益が組み込まれています。
終身保険や養老保険は手数料が非常に高く、資産形成においては「悪手」になりがちです。
さらに「不安を煽る営業」も大きな要因。
保険営業マンは基本的に手数料で成績が決まるため、本当に必要かどうかよりも「契約を取ること」が最優先です。
—
【第6章】資産形成と保険のバランスの考え方
1. まずは公的保障を知る
国民健康保険・社会保険・高額療養費制度・傷病手当金・遺族年金を理解しましょう。
2. 「最悪のケース」だけ保険でカバー
資産形成において大切なのは「小さなリスクは自己負担、大きなリスクは保険で」という発想。
3. 掛け捨てで十分
積立型保険や終身保険は高コスト。保険は「万が一への備え」と割り切り、掛け捨てで安く済ませることが合理的です。
—
【第7章】おすすめの保険と資産形成の組み合わせ
死亡保障(定期保険・掛け捨て)
自動車保険(対人対物無制限)
火災保険(家がある場合)
所得補償保険(自営業者や大黒柱に限る)
それ以外は、現金+投資+iDeCoや新NISAで資産形成していくことを基本にしましょう。
—
【第8章】資産形成を優先し、保険は最低限に
筆者自身も、3人の子供を育てながら資産形成を行っていますが、保険は「死亡保障2,500万円の定期保険(月4,800円)」と「車の保険、車両保険なし年間28030円」と《火災保険》のみです。
医療保険もがん保険も入っていません。
その代わり、NISAや新NISAを最大限活用し、インデックス投資を継続して資産形成をしています。
この方が、結果として数百万単位で家計に差が出ます。
私の例、公的保証を理解してから、保険をほとんど解約しました。積み立て保険を解約したら80万円のマイナスでした!解約金だけをNISAで運用して円安の恩恵もあり2年で利益が80万円!今は5年目で利益が140万円。
—
【第9章】保険見直しのチェックポイント
自分が死亡した場合、困る人がいるか?
1ヶ月以上働けない状態になった場合の生活費はあるか?
公的制度を知っているか?
小さなリスクに大金を払っていないか?
保険料が家計を圧迫していないか?
—
【第10章】結論:資産形成において「保険は守り、投資は攻め」
資産形成において、保険は「守り」であり、必要以上に手厚くするものではありません。
守りを固めすぎると、資産形成のスピードが落ちます。
不要な保険を見直し、その分をインデックス投資や自分のスキルアップに回す方が、結果として家計に大きなプラスをもたらします。
—
【まとめ】
保険は「大きなリスク」だけ備えるもの
守る家族・十分な資産がない場合は死亡保障が必要
小さなリスクは自己負担でOK
積立型保険は資産形成において不利
無駄な保険を解約し、資産運用に回すのが最強の家計防衛策
—
最後にもう一度お伝えします。
**「保険は入るものではなく、リスクを洗い出して最低限だけを選ぶもの」**です。
あなた自身と家族を守りながら、無駄なく効率的にお金を育てていきましょう。
もし具体的な保険見直し相談や家計診断が必要な場合は、ぜひコメントやお問い合わせフォームからご相談ください。
ご覧いただきありがとうございました!
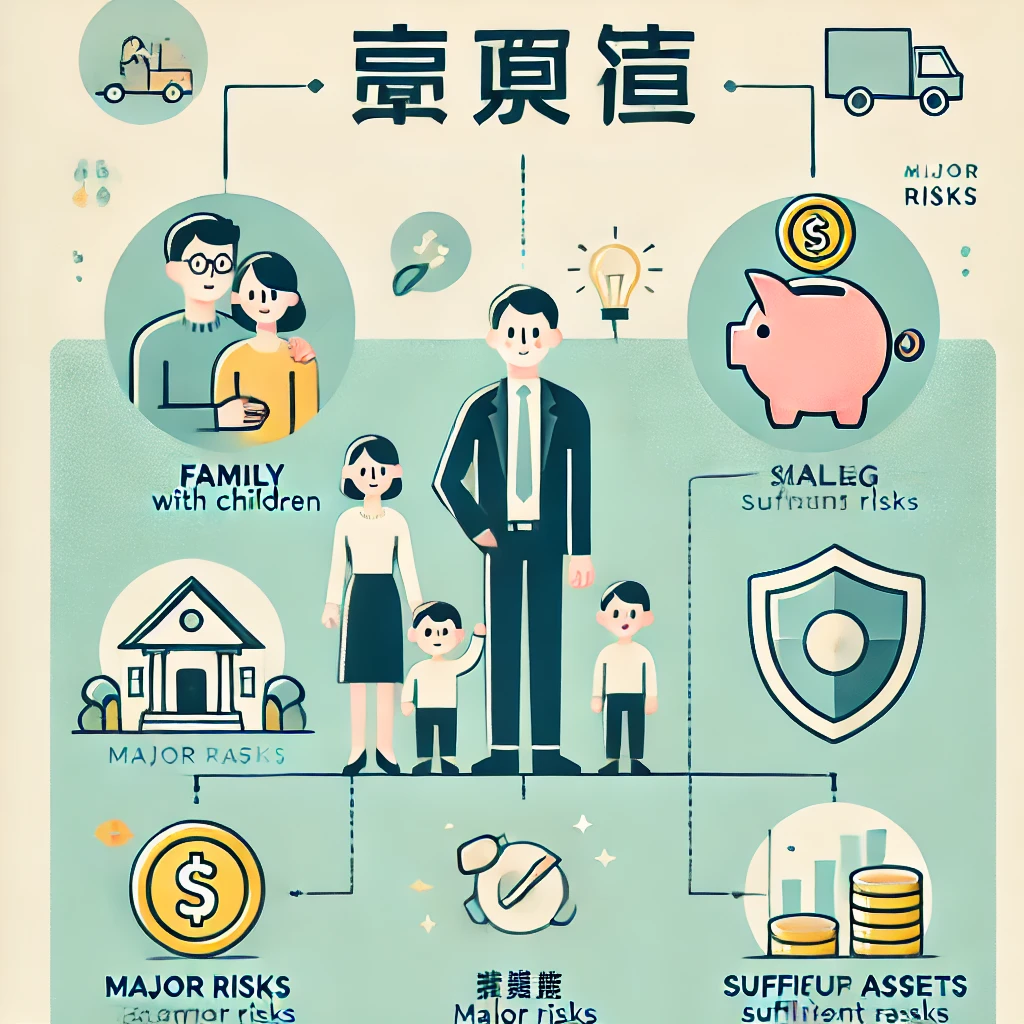


コメント