はじめに
2025年現在、日本の実質金利はマイナス3.5%。そして日本は貿易赤字、少子高齢化、労働時間の減少という構造問題を抱えています。多くの投資家が「米国の利下げがあれば円高に戻るだろう」と考えがちですが、本当にそうでしょうか? 本記事では、1ドル=130円への円高が難しい理由と、逆に1ドル=160円まで円安が進行する可能性について、あらゆる角度から解説していきます。
—
1. 日本の実質金利マイナス3.5%の現実
現在、日本は物価上昇率(CPI)が約3~4%で推移していますが、政策金利は依然として0.5%です。これにより実質金利はマイナス3.5%となっており、これは通貨の価値が目減りしていることを意味します。
マイナス実質金利の主な影響:
円を持っているだけで購買力が減少
海外資産への投資意欲が高まり円売りが発生
円を借りて海外資産を買う「キャリートレード」が加速
米国が利下げを開始したとしても、日本の金利がゼロ近辺である限り、この金利差はまだ大きいままです。米国が3%の利下げをしても、日本は金利0.5%であるため、金利差は2%近く残ります。この差が円安を継続させる要因になります。
—
2. 日本の貿易赤字という現実
かつて「ものづくり大国」だった日本ですが、エネルギー輸入の増大と産業空洞化により、2023年以降、貿易赤字が定常化しています。
2024年実績:
輸出額:輸出数量は一部減少
輸入額:原材料高とエネルギーコスト上昇で増加
年間貿易赤字:5兆円超
貿易赤字は円安圧力を強める大きな要因です。日本企業はドルで仕入れ、円で決済するため、為替の安定には輸出超過が理想ですが、現実は逆行しています。
—
3. 少子高齢化と労働時間減少
人口動態と労働供給の問題
2025年時点で高齢者比率が29%を超える
生産年齢人口はピーク時より15%減少
週休3日制導入議論、労働時間短縮政策が進む
これにより供給サイドの生産力低下が不可避であり、物価上昇圧力が継続します。国内供給力が下がると輸入依存が高まり、為替は円安方向に動きやすくなります。
—
4. 米国の利下げがあっても130円に戻らない理由
米国が2025年後半に利下げを開始するとしても、それは景気悪化が前提です。景気悪化局面では、世界中の投資マネーは「リスク回避」で米ドルに避難する傾向が強まります。
リスク回避時は円買いではなく「ドル買い」
日銀は金利を上げることができず円の魅力は低下
円は「安全資産」から「金利差通貨」へ変化
これらを考慮すると、130円台まで戻す可能性はかなり低いと言えます。
—
5. 逆に170円まで円安になる可能性
あり得るシナリオ
米国の利下げが遅れ、ドル高が継続
日本の貿易赤字が拡大
日銀が利上げできず、国債利払い負担増を恐れて緩和継続
地政学リスク(台湾・中国問題など)が発生し、資源価格高騰
この場合、市場の投機資金が一気に円売りに傾くことは十分にありえます。160円を突破すると「オーバーシュート」で170円台に達する可能性は高いと想定されています。
—
6. 海外勢による円売り・日本株買いの罠
2024年から続く日本株ブームの裏では、実は「円売り・日本株買い」が行われています。
海外投資家は、円を売って日経平均やTOPIXを買い上げていますが、将来的に円安が極端に進んだ場合、利益確定とともに円資産の引き上げ=円売りとなり、さらに円安スパイラルに陥るリスクも。
—
7. 投資家としてどう備えるべきか
資産防衛ポイント
為替リスクを意識して、外貨資産(米ドル・オーストラリアドル・金)を一定割合持つ
国内円資産のみ保有はリスク
インフレヘッジとして金ETF・コモディティETFを活用
住宅ローン残高が多い場合は繰り上げ返済も視野に(住宅価格も上昇します)(固定金利がよさそうです)
国内株投資は輸出関連企業(自動車・半導体関連)を主軸に
—
8. まとめ
実質金利マイナス3.5%、貿易赤字、少子高齢化は円安要因
米国の利下げがあっても130円まで戻る可能性は低い
一方で、オーバーシュートで170円台円安も十分あり得る
投資家は外貨資産・インフレヘッジを意識し、防衛を怠らないことが重要
—
投資は自己責任でお願いします😁
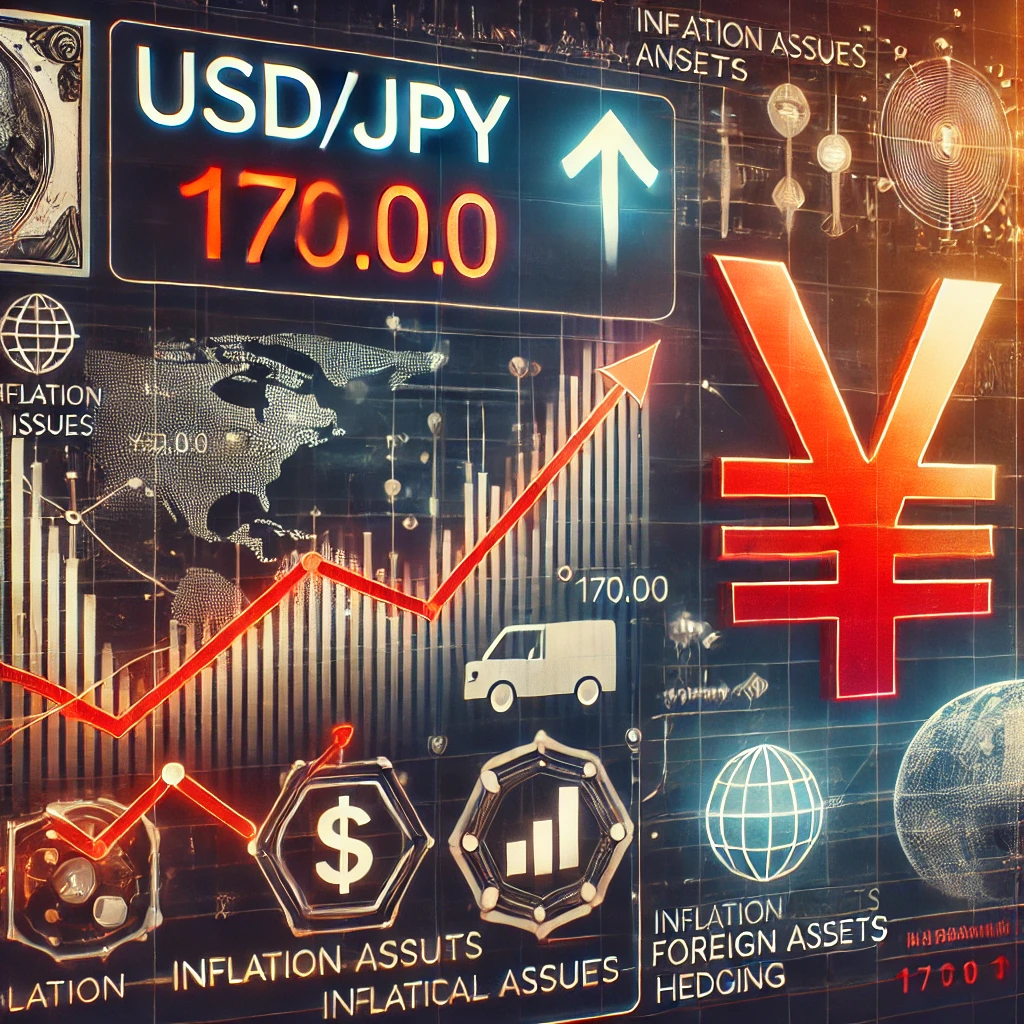


コメント